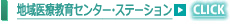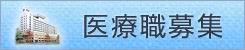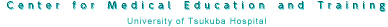研修医の声
2年間の研修を終えた先生に一言いただきました。
臨床研修を振り返って
私は病理学実習で病理診断に興味を持ち、初期研修で病理診断科を回りたいと考えたため、筑波大学附属病院で初期研修を行いました。当院での初期研修の強みは、「プログラムの自由度が高いこと」と「学術活動の機会に恵まれていること」だと感じました。
筑波大学附属病院の初期研修プログラムでは、2年目に診療科ごとに研修病院を選択することができます。他の大学病院や一部の市中病院でも、大学病院と市中病院の両方で研修することは可能です。しかし、診療科ごとに研修病院を選択できるプログラムは比較的少ないのではないかと思います。できることが増えてくる研修2年目に、市中病院でcommon diseaseを診たいのか、それとも大学病院で専門性の高い疾患を診たいのかを診療科ごとに選ぶことができるのは大きなメリットだったと感じています。さらに、複数の病院で研修させていただくなかで多くの先生方からご指導いただいたり、複数の診療スタイル、カルテシステムに触れたりすることができた点も大変有意義でした。
大学病院で研修していた時期では、複数回、学会発表する機会をいただきました。文献の調べ方、スライドの作り方、一つの症例を深めるとはどういうことなのかをゼロから教わりました。さらに、日々のカンファレンスや教授回診で、日々の診療で気づかずに受け流してしまっていた点についても学ぶ機会をいただきました。私の場合、一つの症例を深めることにより他の症例に対してもより多くの疑問が思い浮かぶようになり、学びの好循環が生まれたような気がします。腰を据えて一つのことを深める機会に恵まれているのは大学病院の強みだと思います。
皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。
小児特別プログラム研修医コメント
私は学生時代に5年間小児科ボランティアを行い、授業後に小児科病棟に入院中の子どもたちと遊んだり、勉強を教えていました。そこで出会った長期入院の患者さんと様々なことを話すうちに、自然と小児科医を志すようになりました。初期研修先を選ぶ際に市中病院と大学病院で悩んだのですが、研究・教育に恵まれた環境で働けること、同期の数が多いこと、茨城県内の複数の市中病院で数ヶ月間研修できる自由度の高さから、大学病院を選びました。
小児特別プログラムを選んだ理由は、志望科が小児科と決まっていたことに加え、担当の小児科の先生と相談しながら自分の希望に合わせたローテーションの内容や順番を決められることでした。小児科を異なる現場から学びたいと考えていたので、大学病院では高度医療を提供する新生児科、市中病院ではcommon diseaseを多く扱う一般小児科、外来研修では地域の小児クリニックを選択しました。また小児科と関わりの深い小児外科や産科をまわり、小児外科では実際に手術を執刀させて頂きました。小児科の後期研修医向けの勉強会に参加し、新生児蘇生や鎮静について学ぶことができました。また小児専攻医の先輩方や、小児科の各分野の先生方との繋がりが多くでき、実際に3年目以降小児科医として働くイメージを持つことができました。小児特別プログラムを選択することは、小児科医になることを決めなくてはならないわけではありません。小児科志望の方はもちろんのこと、小児科に興味がある方にぜひお勧めしたいです。ここには共に支え合える多くの友人や、温かく見守ってくれる先生方がたくさんいます。
小児特別プログラムを選択され、皆さんと一緒に働ける日をとても楽しみにしています。
一般プログラム臨床研修医コメント
筑波大学附属病院における研修プログラムの最大の魅力は、大学病院、複数の市中病院を自分の希望に合わせて選択しローテーションを組むことができる自由度の高さにあると思います。
私の場合は、学生時代より循環器内科志望であったため市中病院と大学病院の双方で循環器内科をローテートしました。市中病院では上級医の指導のもとカテーテル検査など多くの手技を経験させていただき、その一方で大学病院ならではの専門的な循環器疾患も経験できる、いいとこ取りのような研修を行いました。また、地域の中核となっている急性期病院から診療所まで合計6か所の病院で研修させていただき、幅広い症例を経験することができました。このような柔軟な病院選択が可能である点が当院での研修の強みであると考えます。
以前、学生さんから「筑波大学での初期研修で医師として成長できたか」という質問を受けました。結論から申しますと、筑波大学の研修プログラムは医師として成長するために十分な環境であり、私自身この2年間を通して大きく成長できたと自負しています。本研修プログラムは前述の自由度の高さは勿論のこと、診療科が豊富にあり希望科を研修できずに悔しい思いをする心配もありません。また、週2回のレジデントレクチャーや屋根瓦式の後輩教育など、教育の文化が根付いております。立地に関しても、つくばエクスプレスを利用すれば都内への移動もスムーズであるため、都内開催の学会や勉強会に参加したいというニーズにも応えられます。
みなさんの2年間が、筑波大学の恵まれた研修環境によって充実したものになりますよう心より願っております。
産科特別プログラム研修修了者コメント
私は5年生の学生実習で産婦人科を回った際、小さな命の誕生に感動し、運命的に産婦人科を志すことを決めました。その気持ちは卒業時にも変わらず、初期研修のうちから、より深く産婦人科について学びたいと思い産科特別プログラムを選択しました。
筑波大学附属病院の初期研修は研修プログラムの自由度が高く、研修したい科・期間・時期を自由に選択することができます。研修する科を選ぶにあたっては、産婦人科の先生方や、研修センターの先生が親身になって、一緒にプランを考えてくださりました。産婦人科医として頻繁に連携をとる科、例えば糖尿病代謝内科、腎臓内科、麻酔科、外科などは通常より長い研修期間を設け、精力的に研修を行いました。そこで勉強したことは、確実に今の診療に役立っています。また産婦人科の研修では、科内の勉強会や学会にも参加させていただき、初期研修医のうちから、後期研修をみすえた研修を行うことができました。
僕のこのプログラムに対する唯一の不満は、ほとんどの診療科で研修先が市中病院でなく、大学病院に限られていたことです。しかし現在はプログラム内容が改訂され、市中病院でcommon diseaseを中心に学ぶことも可能になりました。
今後みなさんと一緒に仕事できる日を楽しみにしています。